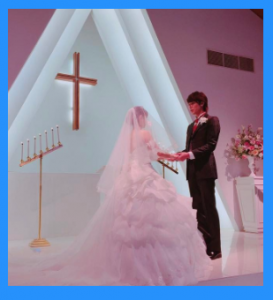2023年1月22日に車いすテニスの国枝慎吾さんが現役引退を表明しました。多くの方が国枝さんを通して車いすテニスという存在を知ったと思いますが、ルールなどはよくわからない方も少なくないと思います。そこで今回は車いすテニスについて健常者のテニスとの違いについてまとめていきます。
車いすテニスと健常者テニスとの共通ルール
違いをまとめる前に共通点をまとめておきます。『テニス』というベースは同様のため、共通点は非常に多いです。
共通点①:コートサイズ、ネットの高さ
同じテニスコートを使用しているためシングルス、ダブルスそれぞれコートサイズ、ネットの高さも同様です。
共通点②:失点のルール
選手の体にボールが触れるルールも車いすにも適用されています。車いすは体の一部と見なされ、ボールが車いす、体に触れたら失点となります。
ちなみに、失点のルールで健常者テニスと車いすテニスで違いがあります。車いすテニスの選手は車いすに体を固定してプレーしていますが、ボールを打つ際にお尻が片方でもシートから浮いたら失点となってしまいます。
共通点③:フォールト
サーブのときに車いすの車輪がベースラインなどに触れるとフットフォールトと同じ扱いになります。ちなみに、サーブをするときはいったん静止し、車いすの車輪を1回だけ押すことが許されています。
車いすテニスとの健常者テニスとの違い
ここからは車椅子テニスと健常者テニスとの違いをまとめていきます。
違い①:2バウンドでの返球もOK
ルールに関して健常者テニスとの最も大きな違いは、車いすテニスでは2バウンドまで認められている点です。2バウンド目はコートの内でも外でも構いません。このルールを逆手にとって1バウンド目で打つと見せかけて、2バウンド目で打つことも戦術として採用されることもあります。
ただ、男子は最近、全体的に競技力が上がっているため、1バウンドでの返球が見られるようになってきました。
違い②:返球の待機姿勢
相手の返球を待つ姿勢は返球した後、相手に背中を向けて後ろ向きに車いすを動かしています。これは健常者なら相手がボールを打ったのを見てサイドステップを使って、ベースラインを右に左に動くことができますが、車いすはそのまま横に動くことができず、しかも、移動に時間がかかることが要因となっています。動き出しをスムーズにするため、後方に車いすを動かしながら返球を待ち、相手の返球を見てその方向に車いすを半円を描くように動かして打点に入り、前に行きながら返球をします。そして再び後方に車いすを動かして相手の返球を待ち、半円を描くように動いて返球するのです。このように半円描くように動くのが車いすテニスの基本の動きになります。こうして半円を描く(動いている)ことで、打点に早く入ることができ、返球をしやすくするだけでなく、前に車いすを動かして打つことで移動エネルギーをボールに伝えることができるから、という利点もあります。
国枝慎吾さんはこのチェアワークが世界一で、それを武器にゴールデンスラムを達成しました。
細かいクラス分けはない
車いすテニスはパラリンピック種目でもあるため、その障害によって階級が異なるように思えますが、実はパラ陸上のような細かいクラス分けはありません。通常の車いすテニスに出場する選手たちは脊髄損傷の部位、足の切断の部位も様々です。そのため、腹筋や背筋などの体幹を使うことができる選手、できない選手が混在している、脚の切断の部位が大きく異なるなど、座った際の体の安定性も選手によって異なっています。しかし、車いすテニスは細かい障害ごとに選手を分けるよりも、大まかなくくりにすることでより多くの選手が自由に参加できるようになっています。そのため、選手の持つ能力に違いが出てきてしまうのは仕方ないとされ、ある意味不公平を承知の上で選手たちは戦っています。
ちなみに、一部クラス分けをされている選手たちがいます。頸髄損傷などで手にも障害を抱える選手は「クアード」と呼ばれています。通常の車いす男子、女子とは別のカテゴリーで男女混合で戦う。クアードの選手はラケットを握る力が弱いため、テープで巻いて手とラケットを固定して戦っています。
最後に
今回は車いすテニスのルールなどについて、健常者のテニスとの違いと合わせてまとめてきました。ほとんどルールの違いがなく、2バウンドまで許可されていることで戦術の幅が広がっている、というのは非常に興味深い内容ではないでしょうか。
国枝慎吾さんの活躍もあり、車いすテニスも非常にレベルが上がってきています。なかなか試合を観戦する機会は多くありませんが、是非チャンスがあれば今回のまとめた内容をもとに観戦してみてもらえれば、と思います!